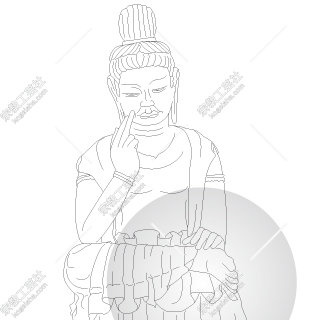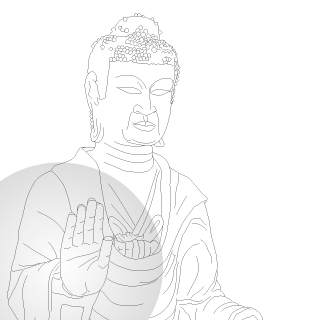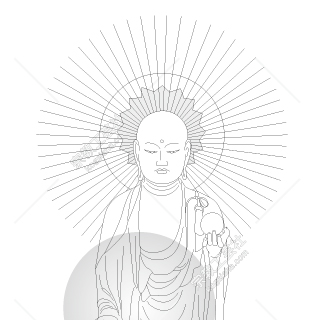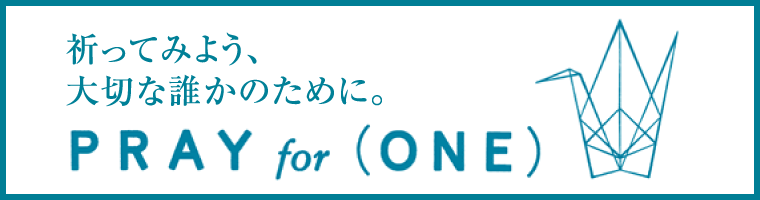飛鳥時代 法隆寺 四天王像(多聞天)
飛鳥時代 法隆寺 四天王像(多聞天) 現存する最古の四天王像。直立不動の姿勢は後世の像とは違い、止利仏師に共通する穏やか作風であるが、 立ち上がった襟は中国・朝鮮半島の武人像に見られるなど、絵画を手本とする可能性もある。
飛鳥時代 広隆寺 弥勒菩薩半跏思惟像(宝髻の弥勒・泣き弥勒)
飛鳥時代 広隆寺 弥勒菩薩半跏思惟像(宝髻の弥勒・泣き弥勒) 広隆寺といえば、国宝「弥勒菩薩半跏思惟像(宝冠弥勒)」だが、 「弥勒菩薩半跏思惟像(宝髻の弥勒・泣き弥勒)」はもう1軀の国宝。 広隆寺を建立した秦河勝が亡くな […]
中国・唐時代 法隆寺 九面観音菩薩立像
中国・唐時代 法隆寺 九面観音菩薩立像 仏教伝来とともにもたらされた請来仏。日本の仏像制作に大きな影響を与えた。 瓔珞など細部にわたり白檀の一材で作られた檀像。 頭上の八面と本面の計九面であるが、十一面観音の原型と考えら […]
飛鳥時代/当麻寺 四天王像・広目天
飛鳥時代 当麻寺 四天王像・広目天 須弥山の四方を守護する四天王はのうち、広目天は西方を守護する。 インド神話の神々が仏教に帰依し守護神となった。 日本最古級の脱活乾漆像で、縮れたあご髭や容貌・衣文など百済から請来したと […]
飛鳥時代/法隆寺 観音菩薩立像(百済観音)
飛鳥時代 法隆寺 観音菩薩立像(百済観音) 杏仁形の目や微笑みは止利様式の名残。「百済観音」と呼ばれるのは江戸時代からで、 それまでは「虚空蔵菩薩」として釈迦三尊像の後ろに北向きで安置されていた。樟(くす)の一木造。
三国時代/関山神社(新潟) 菩薩立像
三国時代 関山神社(新潟)菩薩立像 日本海を渡って移り住んだ渡来人が百済様式の小型金剛仏を請来した。 菩薩像は火災により損傷しているが、法隆寺釈迦三尊脇侍や救世観音の作風と共通する。
飛鳥時代 飛鳥寺 釈迦如来坐像(飛鳥大仏)
飛鳥時代 飛鳥寺 釈迦如来坐像(飛鳥大仏) 飛鳥大仏は蘇我馬子の発願により、600年前後に建てられたという日本最古の寺院飛鳥寺の本尊として 鞍作止利が造ったといわれる、現存する日本最古の仏像。
白鳳時代 法隆寺 観音菩薩立像(夢違観音)
白鳳時代 法隆寺 観音菩薩立像(夢違観音) 江戸時代に書かれた『古今一陽集』には、「この観音像に祈ると悪夢を見ても、吉夢に変えてくれる」とあり、 現在もこの信仰がある。頭上の飾りは正面と左右で「三面頭飾」。
鎌倉時代 西大寺 愛染明王像
鎌倉時代 西大寺 愛染明王像 西大寺の造営・造像と戒律の復興に尽くした叡尊と親交のあった善円の作。 彩色や截金、金銅製の装身具、持物、光背、台座に至るまで造像時のまま残されており、洗練された穏やかな美しさがある。
鎌倉時代/長命寺 地蔵菩薩立像
鎌倉時代 長命寺 地蔵菩薩立像 作者の栄快は快慶の弟子。快慶没後も興福寺・東大寺・薬師寺の大佛師として諸像の造像に関わっており、 その一環として造像されたと考えられる。本像には快慶派の凛とした美しさある。