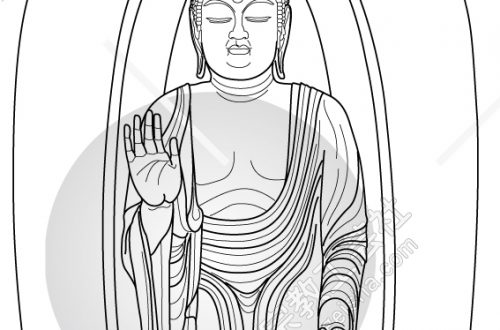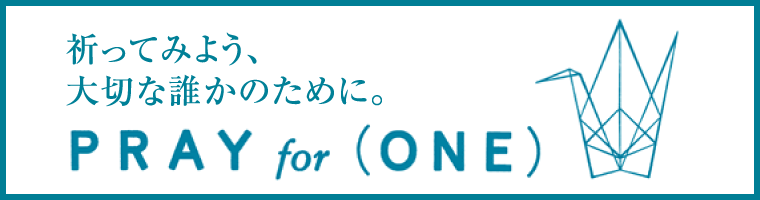平安時代後期 清凉寺 釈迦如来像
平安時代後期 清凉寺 釈迦如来像 宋に渡った東大寺の僧奝然(ちょうねん)は、台州開元寺のインド伝来と伝わる、牛頭栴檀で刻られた釈迦像の瑞像を模刻させ、987年帰国。日本に伝えられたことで、更に多くの模刻像が生み出された。 […]
平安時代前期 清凉寺 阿弥陀三尊像
平安時代前期 清凉寺 阿弥陀三尊像 檜の一木造り。中尊の阿弥陀如来像は光源氏がモデルともいわれている。 印相の定印は平安時代に入ってからのもの。 それまでは施無畏与願印や説法印が多かった。坐像の脇侍は珍しく、印相も余り見 […]
平安時代前期 室生寺 伝釈迦如来立像(薬師如来立像)
平安時代前期 室生寺 伝釈迦如来立像(薬師如来立像) 榧の一木造り。現在、釈迦如来と呼ばれているが、十二神将が随侍しており本来は薬師如来として像造されたもの。薬壺を持たない古式の像であろう。
平安時代 向願寺(渡岸寺) 十一面観音菩薩像
平安時代 向願寺(渡岸寺) 十一面観音菩薩像 檜の一木造り。一般的に十一面観音は頭頂に仏面を表すが、本像は菩薩面とし、 左右耳の後ろに忿怒面・牙上出面を表す。また、耳璫(耳飾り)を付ける。
平安時代/教王護国寺(東寺) 梵天・帝釈天
平安時代 教王護国寺(東寺) 梵天・帝釈天 空海が国を護るため真言密教に基づいた立体曼荼羅として如来・菩薩・明王・四天王とともに造像。 伝統にとらわれない大胆な想像力が発揮されている。木心乾漆像。
平安時代 神護寺 五大虚空蔵菩薩(蓮華虚空蔵菩薩)
平安時代 神護寺 五大虚空蔵菩薩(蓮華虚空蔵菩薩) 虚空蔵菩薩の五つの智恵を五体の菩薩像で表した五大虚空蔵菩薩の内の1体で肉身の色は赤 檜の一木造だが両腕のひじから先は別材、部分的に木屎漆を用いる 金剛界の五智如来の変化 […]
平安時代 観心寺 如意輪観音菩薩
平安時代 観心寺 如意輪観音菩薩 六観音のひとつ 手は六臂で右膝を立てた姿。 乾漆技法を駆使した豊かな体軀、化粧を施したような顔は、この頃からはじまる密教美術の官能的な表現。
平安時代 教王護国寺(東寺) 四天王(広目天・多聞天)
平安時代 教王護国寺(東寺) 四天王(広目天・多聞天) 仏教世界の四方を守る守護神のうち、 右・広目天=「浄天眼」といわれる特別な眼で世の中を観察し、衆生を導き守る「西方」の守護神 左・多聞天=説法の場を整える役割の「北 […]
平安時代 教王護国寺(東寺) 四天王(持国天・増長天)
平安時代 教王護国寺(東寺) 四天王(持国天・増長天) 仏教世界の四方を守る四人の守護神のうち 右・持国天=領土を守り、人々を安心させてくれる「東方」の守護神 左・増長天=生育、増長する力から五穀豊穣を司る「南方」の守護 […]