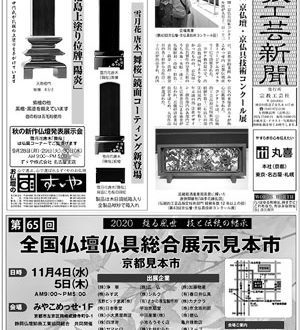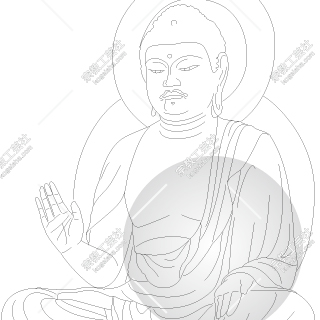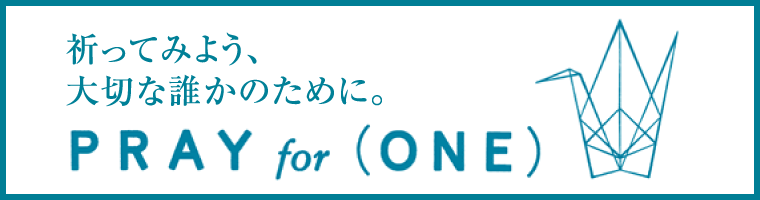鎌倉時代/高徳院 阿弥陀如来坐像(鎌倉大仏)
鎌倉時代 高徳院 阿弥陀如来坐像(鎌倉大仏) 極楽浄土にいて衆生を救済するとされ、多くの信仰を集めた。完成当時は金箔が施され、 大仏殿に安置されていたが、14~15世紀の台風、地震や津波で大仏殿が崩れ、露坐の大仏となって […]
松本商店 和ろうそく・絵ろうそく・華恵香(はなけいか)
松本商店 兵庫県西宮市今津水波町11-3 TEL.0798-36-6021 FAX.0798-26-1338 ホームページ 生掛け和蝋燭で知られているのが兵庫県西宮市の松本商店。松本恭和社長だけではなく、社内の職人さんも […]
櫨蝋燭へのこだわり、そして新たな蝋燭
大與 〒520-1623 滋賀県高島市今津町住吉2-5-8 TEL. 0740-22-0557 FAX. 0740-22-1267 大與ホームページ 大正3年(1914年)大西與一郎が滋賀県高島郡(現高島市)今津町で創 […]
箔座(高岡製箔) HAKU×HAKU ー 箔と箔 ー
箔座日本橋十周年を記念し発表されたのが、「HAKU×HAKU ー箔と箔ー」。純金プラチナ箔、金箔(一号色、四号色、三歩色、定色)、銀箔、銅箔を組み合わせ、二つの箔が持つ光をバイカラー仕立てで魅せるもの。箔の様々な色と輝き […]
宗教工芸新聞2021年6月号(433号)タイトル
《2面》 ▷ソウルジュエリー立川ショールームオープン メモリアルアートの大野屋(立川) ▷京の国宝 守り伝える日本のかたち 京都国立博物館 ▷はせがわ 2021年3月決算 ▷宗教工芸新聞7月号予告 都市型モダン仏壇 ▷洗 […]
奈良時代 葛井寺 千手千眼観音菩薩坐像
千手千眼観音菩薩坐像 奈良時代/葛井寺 日本三大十一面千手千眼観音のひとつ、バランスのとれた美しい仏像は脱活乾漆像の傑作。 千の手・持物は視覚的にも救いの力の大きさを表し、光背のように配された脇手の全ての手のひらには、 […]
宗教工芸新聞2020年9月号(424号)タイトル
《1面》 ▷第43回京仏壇・京仏具技術コンクール展 《2面》 ▷香十天薫堂(銀座・鎌倉) 代表取締役社長に山田昌彦氏が就任 ▷奥居仏具(彦根) 代表取締役に奥居謙太氏が就任(当初掲載にて奥居謙太郎氏と掲載しておりましたが […]
宗教工芸新聞2022年5月号タイトル
《1面》 ▶「母の日参り 俳壇」入選四作品発表 日本香堂(東京) ▶大好評・ウクライナカラーの「魔法のおりんApple」 ウクライナ大使館を通じて売上金の一部を支援金に ずゞや(高松) 《2面》 ▶ソーシャ […]
鎌倉時代 大報恩寺 釈迦如来坐像
鎌倉時代 大報恩寺 釈迦如来坐像 通称千本釈迦堂の本尊。行快作。行快は快慶の仏師系統では筆頭格で、快慶の形式や作風を継承している。 内乱の続く不安定な時代に失われた快慶作の像の再興像。
宗教工芸新聞2020年8月号(423号)タイトル
《1面》暮らしの中の伝統的工芸品展 京仏壇・京仏具 七尾仏壇 高岡銅器 尾張仏具が出展 小田急新宿百貨店 8月19日〜26日 主催・伝統的工芸品産業振興協会 《2面》業界短信 ▶よみがえる正倉院宝物 奈良国 […]